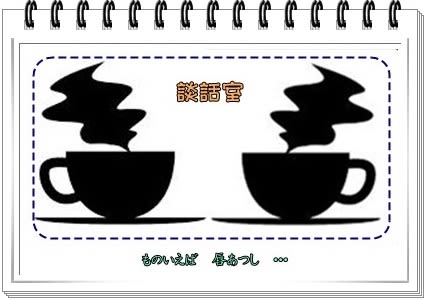
へうげもの
「Hyouge-mono」はラテン文字表記
「 Art Nouveau」
・・フランス語で「新しい芸術」という意味。
アール・ヌーヴォーは、19世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパを中心に開花した国際的な美術運動。「新しい芸術」を意味します。
自然のモチーフや曲線の組み合わせによる従来の様式に囚われない装飾性や、当時の新素材の利用などが特徴。やがて、第一次世界大戦を境に、「アール・デコ」へ。
このアール・ヌーボーに多大な影響を与えたといわれる「ジャポニズム」とは一体なんであったのであろうか?
この「ジャポニズム」の研究では、とりわけ葛飾北斎の版画絵が有名だが、フランスを中心とした西欧の上流階級は、漆器・陶器などの日本美術を「ステータス」として好んだことがとりあげられてています。
ヨーロッパを席巻したジャポニスムはその有機的なフォルム、自然界の参照、当時支配的だった趣味とは対照的なすっきりしたデザインなどで多くの芸術家に大きな影響を与えました。ガレやホイッスラーといった芸術家が直接取り入れたのみならず、日本に着想を得た芸術やデザインはビングやリバティといった商人たちの店によって後押しされました。ビングはアール・ヌーヴォーの店を開く前は日本美術の専門店を経営しており、『芸術的日本』(La Japon Artistique)誌を発行してジャポニスムを広めた、といわれています。
その「有機的なフォルム、自然界の参照」とは、一体何を指すのだろうか、という疑問が?ここをもう少し詳しく見ると・・
「アール・ヌーボー」の強い特色に一つは、左右非対称の調和されたフォルムといわれています。この特色が強く出た作品が世に出ると、西欧の美術界は”強烈”な衝撃を受けたようです。それもその筈、それまでの西欧の美術界は、「ゴチック建築様式」という直線を主体とした様式と絵といえば宗教絵画のみが蔓延しており、それが長い間伝統として君臨してきたわけですから、この異質なモチーフは相当衝撃的であったわけです。”ゴチック”とはまるで正反対なわけです。
「アール・ヌーボー」の時代から遡ること、200~300年前、日本は「安土・桃山時代」あるいは「織・豊時代」とも呼ばれる戦国の末期・でした・・、、、
優れた美術・工芸品を愛した信長を引き継いだ秀吉も、美術工芸品を保護し、振興しました。ただし、秀吉は、「人間の統治の行動原理は、褒賞と恐怖で従順と服従する」と思い込んでいましたが、戦国末期には、戦争も少なくなり、戦勝しても与える領土も限界に達していました。そこで秀吉は、優れた美術工芸品を、褒美にする手法を思いつきます。
秀吉の、邪な発想はともかくとして、この時代は、美術工芸品の作者たちは保護されて、多いに活気づき発展します。自らも優れた芸術家であった千利休は、茶道と芸術を一体化し、その審美眼も鋭いもにがありました。その一番弟子が古田織部です。
・・・「織部は千利休の「人と違うことをせよ」という教えを忠実に実行し、利休の静謐さと対照的な動的で破調の美を確立させ、それを一つの流派に育て上げた。職人や陶工らを多数抱え創作活動を競わせ、優れた作品を作らせた。それとともに人材の育成にも力を注ぎ、小堀遠州、上田宗箇、徳川秀忠、金森可重、本阿弥光悦、毛利秀元らを育てている。
・・・ 博多の豪商、神谷宗湛は、織部の茶碗を見た時、その斬新さに驚き、「セト茶碗ヒツミ候也。ヘウゲモノ也」と、『宗湛日記』に書いている。なお、織部が用いた「破調の美」の表現法に器をわざと壊して継ぎ合わせ、そこに生じる美を楽しむという方法があり、その実例として、茶碗を十字に断ち切って漆で再接着した「大井戸茶碗 銘須弥」や、墨跡を2つに断ち切った「流れ圜悟」がある。・・・織部についての評に「利休は自然の中から美を見いだした人だが作り出した人ではない。織部は美を作り出した人で、芸術としての陶器は織部から始まっている」がある。司馬遼太郎は「おそらく世界の造形芸術史のなかで、こんにちでいう前衛精神をもった最初の人物ではないかとおもう」とその芸術志向を評している。・・・
こんな「織部の美学」が海を渡って、引き継がれている痕跡を見ると、まして「愛されていた」ことを確認すると驚きです。
「ヘウゲモノ」は、ここから生まれたマイナーな用語です。あまり一般的ではありません。
意味を勝手に解釈すれば、破調の美、左右不均衡の調和、歪の美学とでも理解すればいいのかもしれません。
利休が好んだのは、黒や茶の色相。調和されたフォルム。それに対して、織部は、緑がかった色相と不均衡なフォルムに「美の極み」を見つけます。大名としては一流になれなかった織部は、”ゆがみの世界”に、現世の欲に絶望した挫折感と未練が、意外と生々しく残っているようで、人間的で僕は好きです。
『へうげもの』(読みはひょうげもの)、山田芳裕による日本の漫画作品、アニメ。
・第13回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞、
・第14回手塚治虫文化賞マンガ大賞受賞作
漫画なのかと侮るなかれ!どうしてどうして・「鋭くて深い」。
友人からの質問に答えて・・・
昔、大学生になったばかりの頃・・・
高校ではまったく読まなかった「漫画」を夢中で読みました。
まあ!小説や詩集、評論や哲学書など手当たりしだいに読みまくりました。
頭でっかちで観念的で付け焼刃の「言葉」を使ってよく議論したものです。
観念的で付け焼刃の証拠に今はほとんどの語彙を忘れています。
覚えているのは、いくつかの音楽と漫画(アニメ)だけ、、
でも時折、なんかのきっかけで思い出すこともあります。
















